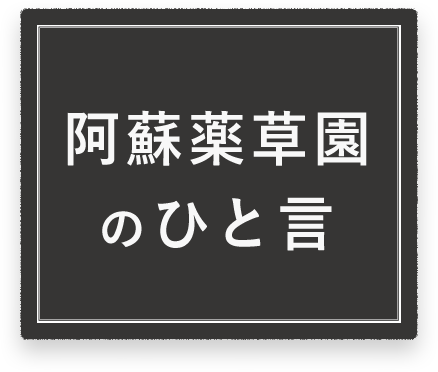大分県南部・熊本県阿蘇地方・宮崎県北部にかけて山間部の限られた地域にのみ自生し、野生のものは絶滅危惧種に指定されています。効能の高さから薩摩藩では「神の草」と呼ばれ、門外不出の秘草として珍重されたそうです。戦後、栽培に成功し、宮崎県では「日本山人参」と名付けられ、本格的な栽培研究が始まったようです。その後、健康食品などの原料としても注目されるようになりました。
この薬草を使ったオススメ商品
利用情報
| 採取時期 | 9月下旬〜11月上旬 |
|---|---|
| 利用部位 | 茎・葉 |
| 利用方法 |
|
| 相性のよい薬草 | よもぎ・とうもろこしのひげ・かきどおし・またたび |
| 注意すること |
|
- ※ 本サイトの情報は、阿蘇薬草園創業者の幼少時代からの経験や、熊本を中心に語り継がれてきた民間薬草の使い方を収集し、実践した内容をもとに、現代に合わせてわかりやすく編集したものを掲載しています。
- ※ 本サイトの記述に基づいて利用される場合は、すべて自己責任の上でご利用ください。事故やトラブルに関しての責任は一切負いかねますので予めご了承ください。
- ※ 不安な方や症状がひどい方は専門医の診察を受け、通院されている方は必ず担当医にご相談の上でご利用ください。
阿蘇薬草園日記
ひゅうがとうき
3/16 月曜日 阿蘇では、昨日の晩から朝にかけて雪が降りました。 こんぺいとうのような粒々の雪で、 日が昇るとすぐに溶けました。 阿蘇薬草園の裏庭では、“ヒュウガトウキ”が芽吹いています。 “ヒュウガトウキ…続きを読む…続きを読む
基本情報
| 生態的特徴 |
多年生植物
|
|---|---|
| 形態的特徴 | 高さ約2m。3年目に親株が開花・結実し、その年の冬にはかれる為、3年以上は育ちません。そのため、収穫業は枯れる前の10月~11月頃に行われます。翌年には1~2年ものの株が成長します。 |