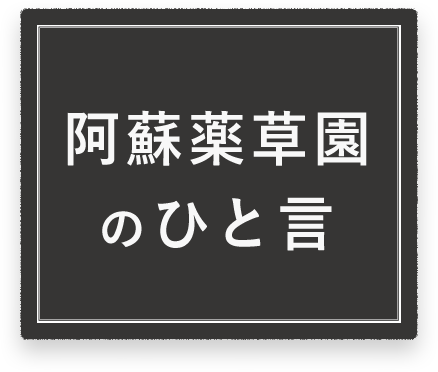熊本では太刀に似ていることから「タチワケ」と呼ばれていました。古くから膿を出す妙薬として知られています。日本には江戸時代に伝来したといわれ、マメ科の中でも最大級の実(さや・豆)がつきます。馴染みがないと思われる方も多いですが、福神漬けの7種野菜の1つであり、健康茶としても人気があります。
利用情報
| 採取時期 | 8月中旬〜10月下旬(霜が降りる前まで) |
|---|---|
| 利用部位 | 根・茎(つる)・葉・花・実(さや・豆) |
| 利用方法 |
|
| 相性のよい薬草 |
|
| 注意すること |
|
- ※ 本サイトの情報は、阿蘇薬草園創業者の幼少時代からの経験や、熊本を中心に語り継がれてきた民間薬草の使い方を収集し、実践した内容をもとに、現代に合わせてわかりやすく編集したものを掲載しています。
- ※ 本サイトの記述に基づいて利用される場合は、すべて自己責任の上でご利用ください。事故やトラブルに関しての責任は一切負いかねますので予めご了承ください。
- ※ 不安な方や症状がひどい方は専門医の診察を受け、通院されている方は必ず担当医にご相談の上でご利用ください。
基本情報
| 生態的特徴 |
蔓性一年草
|
|---|---|
| 形態的特徴 | 葉は長い柄のある複葉3組の小葉。夏、葉の脇から長い柄を出して淡紅紫色~白色の大型の蝶形花を総状につける。実のさやは扁形で長く大きな刀状で湾曲し、30〜50cmほどになる。種子は長さ3cmくらいの円形で、種皮は淡紅色〜白色。 |
| 生薬名 | 刀豆(トウズ) |
| 生薬成分 | タンパク質のグロブリン系、カナバリン、コンカナバリンA,Bなど |
| 用途 | 血液浄化、血行促進、排膿、消炎 |