


生薬名で車前草というとおり、昔は馬車道によく繁殖していたことから、「馬車道草」とも呼ばれていました。長く上に伸びた穂(種)が、水分を含むとくっつき踏まれることで繁殖していきます。おおばこ茶は、ほのかな甘みがあり単品でも飲みやすくやさしい味わいです。
この薬草を使ったオススメ商品
利用情報
| 採取時期 | 全草:5〜8月、種子:10月 |
|---|---|
| 利用部位 | 全草・種子 |
| 利用方法 |
|
| 相性のよい薬草 |
|
- ※ 本サイトの情報は、阿蘇薬草園創業者の幼少時代からの経験や、熊本を中心に語り継がれてきた民間薬草の使い方を収集し、実践した内容をもとに、現代に合わせてわかりやすく編集したものを掲載しています。
- ※ 本サイトの記述に基づいて利用される場合は、すべて自己責任の上でご利用ください。事故やトラブルに関しての責任は一切負いかねますので予めご了承ください。
- ※ 不安な方や症状がひどい方は専門医の診察を受け、通院されている方は必ず担当医にご相談の上でご利用ください。
基本情報
| 生態的特徴 |
多年生草本で、土壌及び気候に対する適応性が高く、日本では寒冷地から暖地まで広く栽培が可能。
|
|---|---|
| 形態的特徴 | 葉は基部がら多数根生し、葉身は長さ4~20cm、幅3~8cmの卵形~広卵形で数本の明瞭な平行脈をもち、生長の良いものでは縁が波打つ。無毛または少量の毛がある。葉柄は、葉身と同じ程度の長さがあり、断面は半月形で内側を囲むようになっている。春から秋にかけて10~50cmの花茎を延ばし、先端から1/3~1/2に白色または薄紫色の風媒花を多数付ける。花は雌性先熟で、下の方から順に開花する。果実は4mm程度のカプセル状で、成熟したものに触れると容易に中央の横線で上部がはずれ、4~6個の黒色の種子がこぼれる。生育状況に応じて葉の大きさなどがさまざまであり、近縁のセイヨウオオバコとの区別に注意が必要である。 |
| 生薬名 | 車前子(シャゼンシ) |
| 生薬成分 | 粘物質(plantasan)、イリドイド配糖体(aucubin, geniposidic acid など)、acteoside、syringing など |
| 用途 | 去痰、消炎、利尿、止瀉、鎮咳薬 |
| 出典 | 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物総合情報データベース(http://mpdb.nibiohn.go.jp/) |


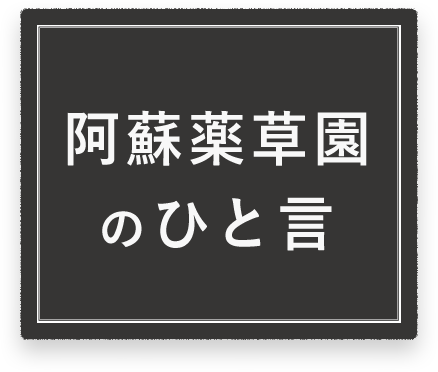
![おおばこ茶(リーフ)15g[箱タイプ]](https://asoyakusouen.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/3eecacd0499d8d6c0eae9edbfa5e0a33.jpg)


